グローバル企業から少人数組織のCTOに挑戦して気づいたこと
NPO法人みんなのコードに参画して、2年半が経ちました。
前職では、グローバルな大手IT企業でエンジニア、そしてマネージャーをしていました。スピード感のある環境で、大きなスケールのプロジェクトに関わる日々は刺激的でした。そして現在は教育に関わるNPOで、子どもたちや先生たちに最新のテクノロジーを届ける活動を送っています。
また同時にビジネス・ブレークスルー大学、清泉女子大学でも准教授として学生の指導にあたっており、大学が本業でNPOがボランティアであるというふうに捉えられる事が多いです。ただ実際の所は週4日はみんなのコードでCTOとして働き、給料も得ており本業になっています。
初めてお会いした方や久しぶりに会った方にこの経緯の説明をする事がおおいので、今日は文章で振り返ってみます。
最初の接点は、ブログ記事とイベント登壇
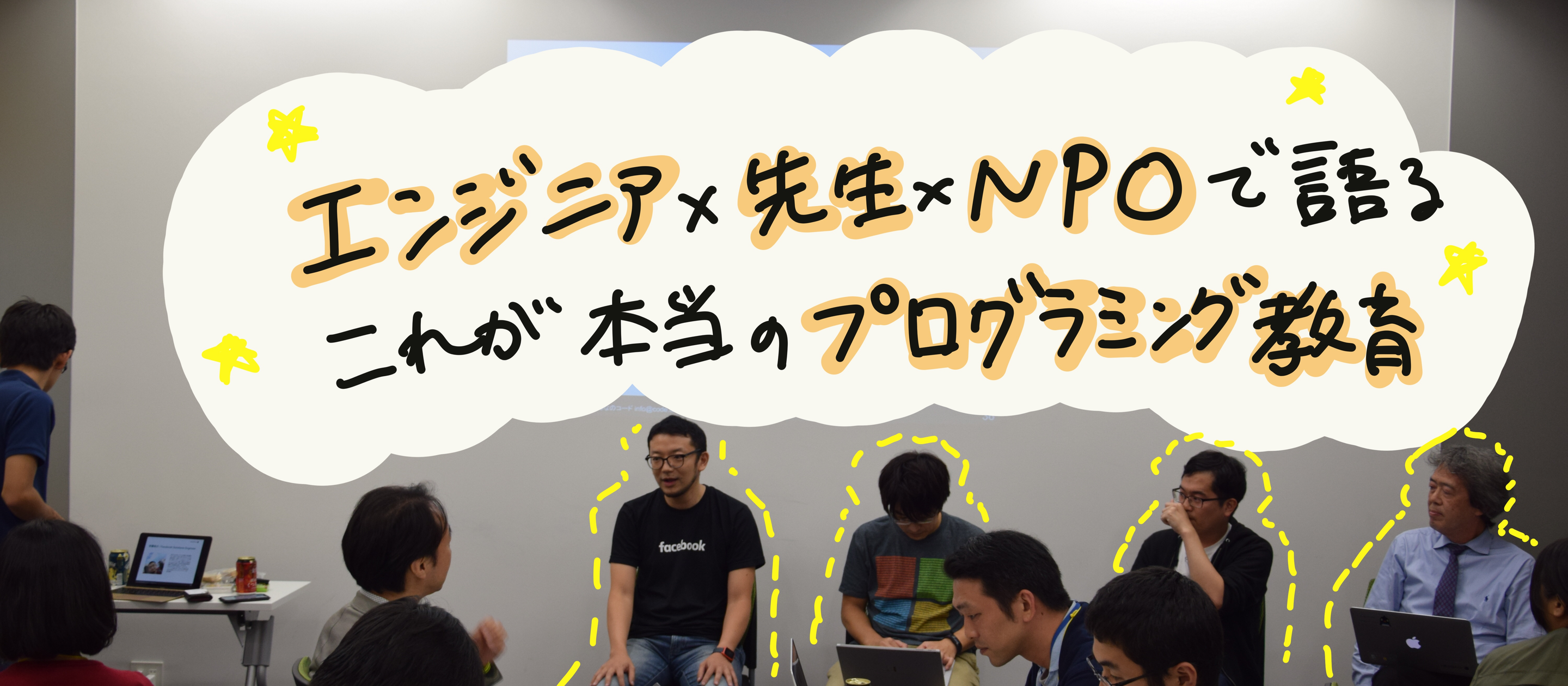
みんなのコードとの最初の接点はイベントでの登壇でした。 学生時代に教員免許を取得したり、その後IT系のスクールでの講師業などをしてきたことからプログラミングを教える事には興味を持っていました。ところが日本でプログラミング教育の話題が盛り上がって来た際に日本の学校教育の制度を知っている人とそうでない人の噛み合わない議論に違和感を持っていました。 そこで書いたのがプログラミング教育と教科書に関するブログ記事です。この記事がきっかけとなってみんなのコードから連絡をもらってイベントに登壇することになりました。イベントでは代表の利根川さんを始め今もお付き合いのある関係者の方々にお会いしました。
その後、別のNPOでプロボノを始め、Slackに前職を退職した事を投稿したメッセージを見た利根川さんから声をかけて頂き、業務委託を経てみんなのコードに入社することになりました。
受益者や協力者への距離感の近さ
みんなのコードで働くようになってもっとも印象的だったのは、価値が提供される現場への近さです。これまで働いてきた営利企業、B2Bの世界では実際に価値が提供されている場面に居合わせる事はあまりありませんでした。みんなのコードでは提供している教材や研修などに触れる学校の先生や生徒の姿を実際に目の当たりすることが数多くあります。 もちろん日本全国の学校現場という視点で言えば、実際に見ているのは一部ではありますが「日本の学校教育」といったものの理解の解像度やどこに課題や価値があるのかと視点が日々アップデートされている感覚があります。
また素朴な概念ではありますが、生成AIやプログラミングという新しい技術に触れた子ども経ちの反応や発想の柔軟さにはいつも驚かされています。
意思決定への責任感
みんなのコードにはオンライン教材の開発と運用を行う技術部という組織があります。CTOとして各プロジェクトの意思決定や開発体制の強化(最近だとコーディングエージェント Devinの導入など)につながる活動はもちろんですが、代表の利根川さん、COOの杉之原さんの3名で幅広い活動に関わっています。
これまで働いてきた企業ではどこであれ、上司や本社、経営陣の意思決定を受けて業務を行うというどうしても受け身で始まる動きが多かったように思います。 一方でみんなのコードでは外部環境の変化や発生した出来事について自分たち自身で意思決定をして取り組む必要があります。自由度が大きいと同時に、社会の変化の把握やさまざまな方との対話の重要性が増すと共に、責任感の重さも感じています。利根川さんの嗅覚や、杉之原さんの経営に関する幅広いスキルと柔軟な対応力にはいつも驚くばかりで、勉強させてもらっている日々です。
やってみようの精神
今日から日本教育工学会の全国大会に参加中。
— Yusuke Ando (@yando) March 2, 2024
朝イチの枠で初めての口頭発表も無事終わり、インプットタイム。
色々な手法や事例を学びたい。 pic.twitter.com/RZZSbmWSLc
毎日、報道されるように生成AIの台頭や少子高齢化で学校など教育にまつわる環境は大きく変化しています。こういった中で時代の変化に合わせた学び方や組織の姿を探る上では新しい事に挑戦するマインドとエネルギーはとても重要です。 個人として挑戦する事はもちろんですが、その挑戦や学びを組織に広げていく事の大事さと効果も感じています。これは入社以前には想像もしていなかった事ですが、生成AIを初めとするAIへのシフト、社内でのAI勉強会の開催、半導体に関する勉強会、AI時代に重要と考えられるワークショップのトライアル、AIに関する資格試験受験の為の社内予備校の開催などさまざまな活動を企画しました。
企画する段階では結果がどうなるのかは予測が難しい部分もありますが、多くのメンバーを巻き込んで学んだ事が、その後組織にとって新しい力になっている事を感じています。 そしてそれを可能にしているのは新しい事を学ぶ事や挑戦してみることに積極的なメンバーがあってこそです。NPOで働くようになって驚き、実感している最も大きな事がメンバーのチャレンジ精神です。
メンバーにチャレンジを促すには自分自身のチャレンジも欠かせません。みんなのコードに入社する前後からは日本教育工学会、情報処理学会、HAIシンポジウム、人工知能学会などの学会に参加したり研究発表をしたりといった事に挑戦し、みんなのコードの活動が明らかにした知見を広く共有する事に挑戦したりもしています。以前はIT系のカンファレンスに参加する事が多かったですが、最近は学術系のイベントに行くことが多く、懐かしい方に再会できることもあって楽しんでいます。
細かいエピソードや日々のアップデートなどもたくさんありますが、そういった事は直接お話する機会などに紹介できればと思います。今回はNPOで元気に働いていますよという報告として終えたいと思います。